
自社株評価は、単なる数字ではなく、税務・財務・経営戦略が複雑に絡み合う領域です。短期的な節税対策だけでは、税務リスクや承継トラブルを招く可能性もあります。だからこそ重要なのは、合法性と合理性を備えた「評価を下げる視点」を、事業承継の全体像の中で設計すること。
本コラムでは、自社株評価の基本から実務で活用できる評価引き下げの考え方、節税と事業承継を両立させるためのポイントを、税務・財務を横断的に支援するMGSの視点で解説します。
contents
この記事の目次
なぜ自社株評価の見直しが重要なのか?

自社株評価は「税金の問題」である前に「経営の問題」
中小企業の事業承継を考える際、多くの経営者が最初に直面する壁が「自社株の評価」です。会社の業績が伸び、内部留保が積み上がるほど、自社株の評価額は高くなり、相続税や贈与税の負担も比例して増加します。これは健全な経営の結果であるにもかかわらず、承継の場面では大きな障害として立ちはだかります。
自社株評価が高いまま承継を迎えると、後継者は多額の税負担を背負った状態で経営をスタートすることになります。場合によっては、納税資金を確保するために借入を行ったり、経営権に関わる株式を分散させざるを得なくなったりするケースもあります。
つまり、自社株評価の問題は単なる「節税」の話ではなく、「経営の安定性」「企業の独立性」を左右する本質的な経営課題なのです。
評価額が高いまま放置されやすい中小企業の実情
自社株評価は、上場企業の株価のように日々意識されるものではありません。そのため、多くの中小企業では「税理士に言われるまで評価額を知らなかった」「相続が現実になって初めて問題に気づいた」という状況が少なくありません。
特に、長年にわたり黒字経営を続けてきた企業や、堅実に内部留保を積み上げてきた企業ほど、自社株評価が想定以上に高額になっているケースが多く見られます。
経営者自身は「まだ承継は先の話」と考えていても、評価額は毎期の決算によって積み上がり、気づいたときには対策の選択肢が限られてしまうこともあります。
このように、自社株評価は「見えにくいリスク」であるがゆえに、早期の見直しが重要になります。
自社株評価は「直前対策」では間に合わない
自社株評価の見直しで最も重要なポイントの一つが、「時間軸」です。評価額は、利益水準や純資産、配当方針など、複数年にわたる経営結果の積み重ねによって形成されます。そのため、承継直前になって急に対策を講じても、大きな効果を得ることは難しいのが実情です。
例えば、役員退職金の支給や設備投資などによる評価調整も、計画的に進めなければ税務上の合理性を欠くと判断されるリスクがあります。短期的な節税だけを狙った施策は、税務調査で否認される可能性を高めるだけでなく、会社の財務体質を不安定にすることにもつながります。
だからこそ、自社株評価の見直しは「事業承継の数年前」ではなく、「事業承継を意識し始めた段階」から着手することが望ましいのです。
評価を下げること自体が目的になってはいけない理由
自社株評価の話題になると、「どうすれば評価を下げられるのか」という点に意識が集中しがちです。しかし、評価を下げること自体が目的化してしまうと、本来守るべき経営の健全性が損なわれる恐れがあります。
評価額は、あくまで会社の実態を反映した結果です。無理な利益調整や不自然な資産処分は、短期的には評価を下げられるかもしれませんが、長期的には企業価値を毀損し、承継後の経営を難しくしてしまいます。
重要なのは、「会社の将来像に沿った形で、結果として評価が適正化されている状態」を目指すことです。
事業承継を見据えた評価設計という考え方
自社株評価の見直しは、税務・財務・経営戦略を一体で考える必要があります。役員報酬や退職金の設計、配当政策、資金調達、組織再編など、日々の経営判断そのものが評価額に影響を与えます。
そのため、評価対策は単発の施策ではなく、「事業承継計画の一部」として設計されるべきものです。将来どのタイミングで、誰に、どのような形で株式を承継するのか。その全体像を描いた上で、評価の推移をコントロールしていくことが、結果的に最も安全で効果的な節税につながります。
自社株評価を正しく理解し、早い段階から見直しに取り組むことは、経営者自身の安心につながるだけでなく、後継者が健全な形で経営を引き継ぐための重要な準備です。
お問い合わせはこちら自社株評価の基礎知識 − 評価方法と押さえるポイント

自社株評価は「税務上のルール」に基づいて算定される
自社株の評価は、経営者の感覚や市場価値で決まるものではありません。相続税・贈与税の計算に用いられる自社株評価は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて算定されます。
つまり、自社株評価は明確なルールに沿って算出される“税務上の数字”であり、恣意的に操作できるものではないという前提を理解することが重要です。
一方で、この評価ルールを正しく理解すれば、どの要素が評価額に影響し、どこに改善の余地があるのかが見えてきます。自社株評価の見直しとは、ルールの抜け道を探すことではなく、「評価の仕組みを踏まえた上で経営を整えること」だと言えるでしょう。
中小企業で主に使われる3つの評価方法
非上場株式である自社株の評価方法にはいくつか種類がありますが、中小企業で実務上よく用いられるのは、主に次の3つです。
類似業種比準方式
類似業種比準方式は、上場企業の株価や財務指標を基準に、自社の利益・配当・純資産を比較して評価する方法です。中規模以上の会社では、この方式が適用されるケースが多くなります。
この方式の特徴は、「収益力」が評価に大きく影響する点です。安定して利益を出している会社ほど評価は高くなりやすく、反対に利益水準が下がれば評価額も下がります。
そのため、役員報酬の設計や利益配分の考え方が、評価額に直結しやすい評価方法だと言えます。
純資産価額方式
純資産価額方式は、会社の貸借対照表をもとに、資産から負債を差し引いた「純資産」を基準に評価する方法です。小規模な会社や資産を多く保有している会社では、この方式が適用されることがあります。
この方式の特徴は、過去の利益の積み重ねや保有資産がそのまま評価額に反映される点です。不動産や有価証券などの資産を多く持つ企業では、思った以上に評価が高くなることも少なくありません。内部留保を厚くしてきた企業ほど、評価が下がりにくい構造になっています。
配当還元方式
配当還元方式は、主に少数株主が保有する株式の評価に使われる方法です。配当実績を基に評価するため、支配株主が持つ株式には原則として適用されません。ただし、株式の分散状況によっては、承継設計に影響するケースもあるため、全体像の理解として押さえておく必要があります。
評価方法は「会社規模」で決まる
どの評価方法が適用されるかは、会社の規模区分(大会社・中会社・小会社)によって決まります。この規模区分は、従業員数や総資産額、売上高など複数の指標によって判定されます。
重要なのは、「評価方法を選べるわけではない」という点です。会社の実態に応じて評価方法が決まるため、規模区分そのものが評価額に大きな影響を与えます。場合によっては、規模区分が変わるだけで評価額が大きく変動することもあります。
自社株評価に影響する3つの主要ポイント
評価方法を理解した上で、次に押さえておきたいのが「何が評価額を動かすのか」という点です。自社株評価に大きく影響する要素は、主に次の3つに整理できます。
① 利益(収益力)
利益は、類似業種比準方式において特に大きな影響を持つ要素です。単年度の利益だけでなく、一定期間の平均値が使われるため、継続的な利益水準が評価に反映されます。
② 純資産(内部留保・資産内容)
純資産は、純資産価額方式だけでなく、類似業種比準方式の比準要素にも影響します。内部留保の積み上がり方や、資産の中身(現預金・不動産・有価証券など)が評価額を左右します。
③ 配当
配当は見落とされがちですが、評価計算上は重要な要素です。配当方針は、評価額だけでなく、株主構成や承継後の資金繰りにも影響するため、慎重な設計が求められます。
「評価の仕組み」を知ることが戦略の第一歩
自社株評価の基礎を理解することで、「なぜ自社の株価が高いのか」「どの要素に手を打つべきか」が見えてきます。評価を下げる施策は、この仕組みを無視しては成り立ちません。
自社株評価の見直しとは、数字を操作することではなく、会社の経営と財務を整理し、将来に向けて最適な形に整えていくプロセスです。
実務で効く!自社株評価を下げる方法

自社株評価を下げる方法と聞くと、どうしても「節税テクニック」や「裏技」を探したくなりがちです。しかし実務の現場では、評価を下げるためにやるべきことは、決して特別なことではありません。むしろ、評価の仕組みを理解したうえで、経営・財務を正しく整えることが、最も安全で効果的な方法となります。
ここでは、中小企業の事業承継支援の現場で実際に用いられている代表的な考え方を、評価への影響とあわせて整理します。
① 利益をコントロールするという考え方
自社株評価、とりわけ類似業種比準方式では「利益」が大きなウエイトを占めます。そのため、利益水準の設計は評価対策の基本中の基本です。
役員報酬の最適化
役員報酬は、会社の利益を調整する代表的な手段です。適正な範囲で役員報酬を引き上げることで、利益を圧縮し、結果として評価額を抑える効果が期待できます。
ただし、過度な増額は「不相当に高額な役員報酬」として否認されるリスクがあります。評価対策として有効に機能させるためには、職務内容や業績との整合性を持たせることが不可欠です。
役員退職金の活用
将来の承継を見据えた対策として、役員退職金の設計も重要です。退職金は損金算入が可能であり、利益・純資産の双方に影響を与えるため、評価引き下げ効果が高い施策の一つです。
ただし、こちらも金額の妥当性や支給時期を誤ると税務リスクが生じるため、事前のシミュレーションと計画性が欠かせません。
② 純資産を意識した財務設計
純資産価額方式が適用される場合はもちろん、類似業種比準方式においても純資産は重要な評価要素です。内部留保が厚くなるほど評価が下がりにくくなるため、資産構成の見直しがポイントになります。
含み損資産・遊休資産の整理
長年保有している不動産や有価証券の中には、帳簿上は高く見えても、実際には含み損を抱えているものもあります。こうした資産を整理することで、評価額の適正化につながるケースがあります。
また、事業に直接関係しない遊休資産を見直すことは、評価対策だけでなく経営効率の改善にも寄与します。
借入金の活用という視点
借入金は純資産を圧縮する要素となります。設備投資や事業拡大に伴う合理的な借入であれば、評価対策としても意味を持ちます。
ただし、「評価を下げるためだけの借入」は本末転倒になりやすいため、あくまで経営上の必要性が前提となります。
③ 配当政策の見直しが評価に与える影響
配当は、評価計算上の要素でありながら、実務では見落とされがちなポイントです。配当実績が高いと評価額が上がりやすくなるため、承継を見据えた配当政策の設計が重要になります。
一方で、配当をゼロにすればよいという話ではありません。株主構成や資金繰り、後継者の立場などを踏まえ、長期的なバランスを取ることが求められます。
④ 組織再編・持株会社化という選択肢
一定規模以上の企業では、組織再編や持株会社化を通じて評価構造そのものを見直すケースもあります。事業と資産を分離することで、承継対象となる会社の評価を適正化できる場合があります。
ただし、組織再編は高度な税務判断を伴い、目的や手順を誤ると大きなリスクを招きます。評価対策として検討する場合は、事業承継全体の設計の中で慎重に進める必要があります。
⑤ 「評価を下げる」のではなく「評価を整える」という視点
実務で最も重要なのは、「評価を下げること自体」を目的にしないことです。評価はあくまで会社の実態を映す結果であり、健全な経営判断の積み重ねが、結果として評価の適正化につながります。
短期的な数字合わせではなく、将来の経営、後継者の負担、会社の持続性まで見据えた対策こそが、最も効果的な自社株評価対策です。
お問い合わせはこちら注意すべき税務リスクと否認対策
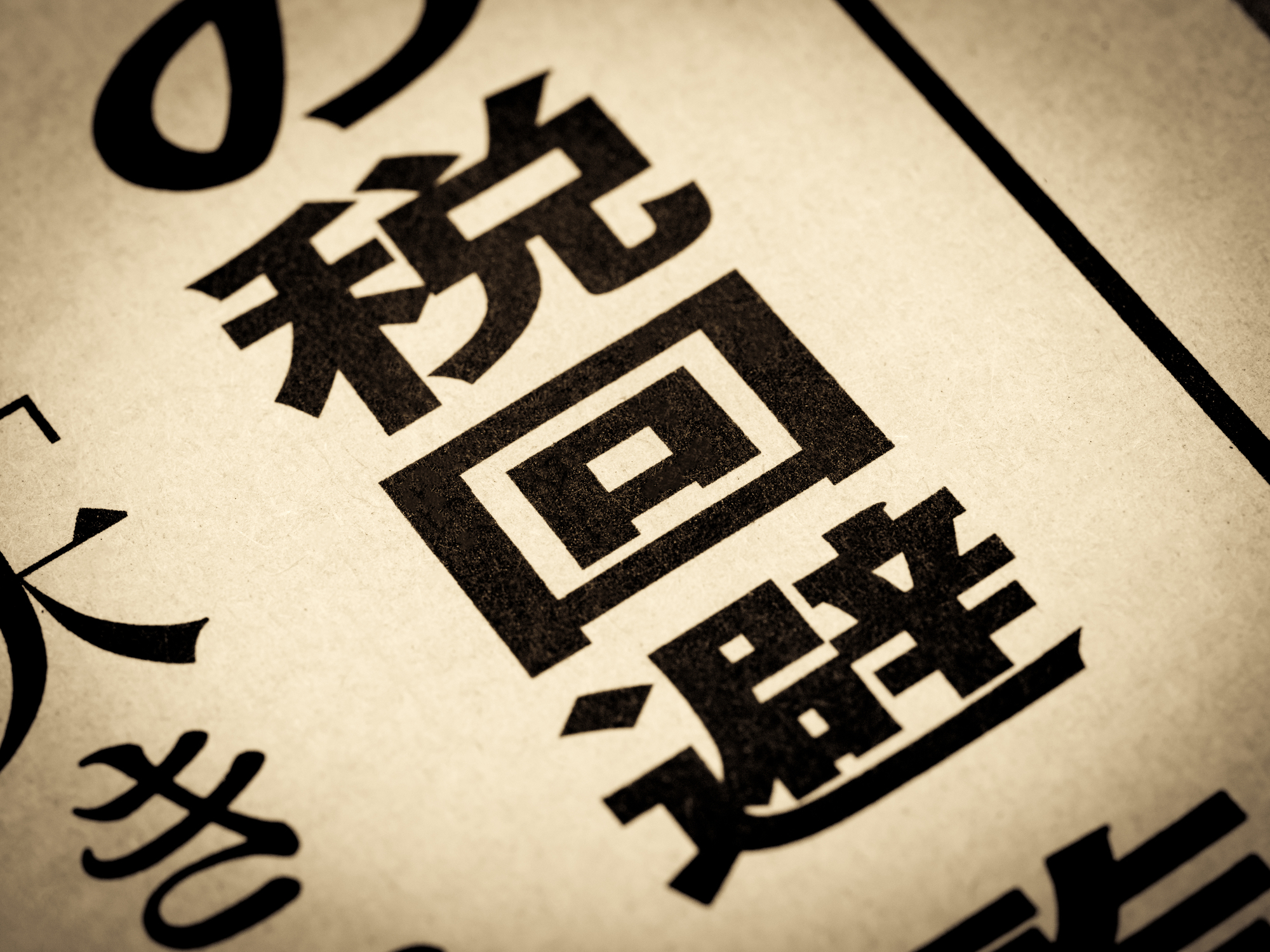
自社株評価を下げる対策は、正しく行えば事業承継を円滑に進めるための有効な手段になります。一方で、進め方を誤ると「節税のつもりが、結果的に否認されてしまった」という事態にもなりかねません。
ここでは、実務の現場で特に注意すべき税務リスクと、その回避策について整理します。
「評価を下げたい」という意図が前面に出るリスク
税務上、自社株評価を引き下げること自体が問題になるわけではありません。しかし、その目的や過程に合理性がない場合、税務署から厳しくチェックされる対象となります。
節税ありきの対策は否認されやすい
例えば、事業の実態や将来計画と無関係に、評価引き下げだけを目的として利益を圧縮した場合、「租税回避行為」と判断される可能性があります。
役員報酬や退職金の急激な増額、必要性の乏しい資産処分などは、その代表例です。
税務署が重視するのは、「その取引や判断に、経営上の合理的理由があるかどうか」です。評価対策であっても、経営判断として説明できない施策は、結果的に否認リスクを高めてしまいます。
役員報酬・退職金に関する否認リスク
自社株評価対策としてよく使われる役員報酬や退職金は、税務リスクが顕在化しやすい項目です。
不相当に高額な役員報酬
役員報酬が職務内容や会社規模、業績に照らして過大と判断されると、損金不算入とされる可能性があります。特に、承継直前のタイミングで急激に報酬を引き上げた場合は、税務調査で注目されやすくなります。
退職金の金額・支給時期の妥当性
役員退職金についても、算定根拠が曖昧なまま高額な金額を設定すると否認リスクが高まります。
在任年数、最終報酬月額、同業他社との比較など、客観的な基準に基づく設計が不可欠です。
資産の移動・処分に関する注意点
評価引き下げの一環として資産の売却や移転を行う場合、その取引条件やタイミングには特に注意が必要です。
不自然な資産処分は疑われやすい
含み損のある資産を処分すること自体は問題ありませんが、第三者との取引条件が不自然であったり、承継直前に集中して行われたりすると、税務上の疑義を持たれることがあります。
関連当事者間取引のリスク
親族間やグループ会社間での資産移転は、価格の妥当性や取引目的が問われやすい領域です。時価評価や契約書の整備など、形式面も含めた慎重な対応が求められます。
「説明できる対策」であるかが最大の防御策
税務リスクを回避するうえで最も重要なのは、「第三者に説明できるかどうか」という視点です。
経営判断としての一貫性
評価対策は、単独で存在するものではなく、事業計画や資金計画、承継計画と連動している必要があります。
「なぜその施策を行ったのか」「会社にとってどんな意味があるのか」を論理的に説明できる状態を作ることが、最大の否認対策になります。
証拠書類・記録の重要性
議事録、契約書、シミュレーション資料など、判断の裏付けとなる資料を残しておくことも重要です。税務調査では、結果だけでなく「過程」が問われます。
短期視点ではなく長期視点で考える
自社株評価対策は、短期的に数字を動かすものではなく、数年単位で評価の推移をコントロールしていくものです。
短期的な節税効果だけを追い求めるほど、税務リスクは高まります。
長期的な視点で、会社の成長と承継の両立を図ること。それが結果として、最も安全で確実な自社株評価対策につながります。
節税効果を最大化する事業承継との組み合わせ方

自社株評価を下げる施策は、それ単体で完結するものではありません。真に効果を発揮するのは、「いつ・誰に・どのように事業を引き継ぐのか」という事業承継全体の設計と組み合わせたときです。
ここでは、自社株評価対策を事業承継とどう結びつけるべきか、その考え方を整理します。
「評価を下げるタイミング」が節税効果を左右する
事業承継における節税効果は、「何をやるか」だけでなく「いつやるか」によって大きく変わります。
自社株評価は毎期の決算内容をもとに算定されるため、評価が下がった“後”に株式を移転することが重要です。
例えば、評価対策を講じたものの、株式の贈与や相続がその前後でずれてしまうと、期待していた節税効果が十分に得られないことがあります。
だからこそ、評価の推移を見据えながら、贈与・相続・持株移転のタイミングを事前に設計する必要があります。
贈与・相続・譲渡をどう使い分けるか
株式承継の方法には、主に「贈与」「相続」「譲渡」があります。それぞれ税務上の特徴が異なるため、自社株評価対策と組み合わせて検討することが重要です。
贈与との組み合わせ
評価が下がったタイミングでの贈与は、節税効果が非常に高くなります。特に、段階的な贈与を行うことで、後継者への負担を分散させることが可能です。
ただし、贈与税の負担や資金面も考慮し、無理のない設計が求められます。
相続との組み合わせ
相続はタイミングを選べないという特性があります。そのため、生前から評価をコントロールしておくことが何より重要です。評価対策が不十分なまま相続を迎えると、納税資金の問題が一気に顕在化するため、早期の準備が不可欠です。
譲渡という選択肢
後継者が十分な資金力を持つ場合や、持株会社を活用する場合には、譲渡が有効なケースもあります。譲渡価格と評価額の関係を整理しながら、税負担と経営権のバランスを取ることがポイントです。
事業承継税制との関係性を正しく理解する
事業承継税制は、条件を満たせば相続税・贈与税の納税を猶予・免除できる制度ですが、「使えば安心」という万能薬ではありません。評価額そのものが下がるわけではないため、将来の制度変更リスクや、要件を満たし続ける負担も考慮する必要があります。
そのため、自社株評価を適正化したうえで、必要に応じて事業承継税制を組み合わせるという考え方が、実務上は現実的です。
自社株評価対策は「事業承継計画の一部」である
最も重要なのは、自社株評価対策を単独の節税施策として扱わないことです。
後継者の育成状況、経営体制、会社の成長フェーズなどを踏まえ、事業承継計画全体の中で評価をどう位置づけるかを考えることで、無理のない節税と円滑な承継が両立します。
評価を下げることはゴールではありません。後継者が安心して経営を引き継ぎ、会社が持続的に成長していくことこそが、本来の目的です。
まとめ
自社株の評価を下げる方法と節税対策は、正しい知識と計画性があれば、事業承継を大きく前進させる武器になります。一方で、評価の仕組みを理解しないまま対策を進めると、税務リスクや承継トラブルを招く恐れもあります。
重要なのは、
・自社株評価の仕組みを正しく理解すること
・評価対策を短期ではなく長期視点で設計すること
・事業承継全体の計画と一体で考えること
この3点です。
自社株評価対策は、単なる節税テクニックではなく、「次世代へ会社をどう引き継ぐか」という経営者の意思を形にするプロセスです。早い段階から専門家とともに全体像を描くことで、無理のない承継と、将来にわたる安心を実現することができます。
MGS税理士法人は、後継者選定・税務対策・株式承継・法務手続きまで一括支援。
独自の「10ヵ年カレンダー」で長期的・計画的な事業承継を実現。専門家連携で税務・法務を包括支援し、M&Aや株式移転も対応しています。
事業承継の実務ノウハウは、書籍でも公開しています。
事業承継に関する、ご相談はMGS税理士法人まで、お気軽にお問い合わせください。








